管理人がつれづれに書き散らかしたあれこれ
2025.11.23
[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
2008.03.24
ゲームとパズルの関係
前回は「何故Aマホはパズルっぽいのか?」というのをメインにした記事でしたが、今回はちょっと視点を変えた話です。
やっぱり内容は「何故Aマホはパズルっぽいのか?」の延長線上にあるのですが。
やっぱり内容は「何故Aマホはパズルっぽいのか?」の延長線上にあるのですが。
まずは用語のおさらいから。
前回は
と定義しました。
実はゲームに関してはもう少し別の考えを持っているのですが、前回の話では関係がないので割愛しました。が、今後絡んでくる可能性があるので再度ゲームという言葉について以下の意で用いることを宣言します。
一人遊びのTVゲームですら、「近隣の迷惑にならぬようボリュームを下げる」程度の社会性は必要なわけです。
私はゲームと名のつくものはすべからく社会性を要求されると考えています。
…話と関係あるかどうかは別ですが。
話の混乱を避けるために、次の点を最初に断っておきます。
・考える(意志決定)だけではゲームとは呼ばない。考えるだけならパズルで充分。
・最適解が存在するものはすべからくパズルに通じる。解は常に一とは限らない。
これが私の立場です。
ゲームに対する要求が厳しいと感じるかもしれませんが、それについては本編で。
そもそも、ゲームとパズルの関係はどうなんだ?
いろいろと話が混迷する原点はここにあると思います。
ですので、あくまでも私見ですがちょっと整理してみましょう。
パズルもゲームも遊びには違わない、ということに付いては同意が得られやすいと思っています。
本当は図にすると解りやすいのですが諸般の事情があるので文だけで勘弁を。
遊び(遊戯)全体を一つの群れと見なします。
便宜上「群α」と呼びましょう。
次にゲームもまた全体を一つの群れと見なします。
ゲームは群αに所属するもので、これを「群G」と呼びます。
さらに、TRPGもまた一つの群れと見なします。
これは群Gに所属するものです。TRPGの群れは「群g」と呼びます。
続いてパズルも全体を群れと見なします。
これもゲームと同じく群αに所属するもので、これを「群P」と呼びます。
この群Pには、水平思考推理パズルが所属しています。
これも全体を群れと見なし「群p」と呼ぶことにします。
群α=群G+群P
さて。
群Gと群Pは完全に別のものでしょうか?
少なくとも、私は違うと思っています。
群β=群G且つ群P
上に示した様に、どちらの性質も持っている群の所属要素が存在していると考えています。
そして、これこそが「Aの魔法陣はなぜパズル的か?」の答えだと私は考えています。
つまり。
群βは群gの一部を含む
群βは群pの一部を含む
と考えたとき、
Aの魔法陣=群g且つ群β
なのだろう、と思うのです。
この点は他のシステムについても言えると思っています。
激しく・派手で・厳しい戦闘を売りとしているシステムに関しては他はどうあれ戦闘部分だけ切り出せばパズルでしょう。
ところで、Aの魔法陣に関してパズルっぽく感じるもうひとつの理由を挙げてみます。
それは「システム自体が一定のルールを規定していない」ことにあると考えます。
最初に定義したとおり、ゲームとは一定のルールのもとで運用されるものと考えます。
つまり、文字が読める或いは言語を理解できるならば
・誰がいつどのようなメンバーと
遊んだとしても「同じ運用」になるものが「一定のルール」と呼ぶものなのではないでしょうか。
将棋の香車を斜めに動かして良い、オセロの駒は挟めるものがなくても置いて良い。そんな運用は聞いたことがないように、ゲームのルールとは常に一様の運用をされてしかるべきと考えます。
(だからこそ、システムが自分の希望と合致しないならば別のシステムを探せ、と言います。枝葉末節ならばともかくシステムの根幹に手を入れるのは私にとって言語道断の行為です)
故に、恣意と舌先で運用が変わるシステムであるAの魔法陣は、ゲームっぽくないのです。
前回は
ゲームとは、勝ち負けを伴う娯楽であり、一定の方法(=明確なルール)で行う遊びである。
パズルとは、文字・絵・言葉等を用い謎(=命題)を提示し、それに対し思考を以て判断を行うものである。
と定義しました。
実はゲームに関してはもう少し別の考えを持っているのですが、前回の話では関係がないので割愛しました。が、今後絡んでくる可能性があるので再度ゲームという言葉について以下の意で用いることを宣言します。
ゲームとは、勝ち負けを伴う娯楽であり、一定の方法(=明確なルール)で行う遊びである。
また、その(=プレイ)課程において一定の社会性が求められ、かつ身につく遊びである。
一人遊びのTVゲームですら、「近隣の迷惑にならぬようボリュームを下げる」程度の社会性は必要なわけです。
私はゲームと名のつくものはすべからく社会性を要求されると考えています。
…話と関係あるかどうかは別ですが。
話の混乱を避けるために、次の点を最初に断っておきます。
・考える(意志決定)だけではゲームとは呼ばない。考えるだけならパズルで充分。
・最適解が存在するものはすべからくパズルに通じる。解は常に一とは限らない。
これが私の立場です。
ゲームに対する要求が厳しいと感じるかもしれませんが、それについては本編で。
そもそも、ゲームとパズルの関係はどうなんだ?
いろいろと話が混迷する原点はここにあると思います。
ですので、あくまでも私見ですがちょっと整理してみましょう。
パズルもゲームも遊びには違わない、ということに付いては同意が得られやすいと思っています。
本当は図にすると解りやすいのですが諸般の事情があるので文だけで勘弁を。
遊び(遊戯)全体を一つの群れと見なします。
便宜上「群α」と呼びましょう。
次にゲームもまた全体を一つの群れと見なします。
ゲームは群αに所属するもので、これを「群G」と呼びます。
さらに、TRPGもまた一つの群れと見なします。
これは群Gに所属するものです。TRPGの群れは「群g」と呼びます。
続いてパズルも全体を群れと見なします。
これもゲームと同じく群αに所属するもので、これを「群P」と呼びます。
この群Pには、水平思考推理パズルが所属しています。
これも全体を群れと見なし「群p」と呼ぶことにします。
群α=群G+群P
さて。
群Gと群Pは完全に別のものでしょうか?
少なくとも、私は違うと思っています。
群β=群G且つ群P
上に示した様に、どちらの性質も持っている群の所属要素が存在していると考えています。
そして、これこそが「Aの魔法陣はなぜパズル的か?」の答えだと私は考えています。
つまり。
群βは群gの一部を含む
群βは群pの一部を含む
と考えたとき、
Aの魔法陣=群g且つ群β
なのだろう、と思うのです。
この点は他のシステムについても言えると思っています。
激しく・派手で・厳しい戦闘を売りとしているシステムに関しては他はどうあれ戦闘部分だけ切り出せばパズルでしょう。
ところで、Aの魔法陣に関してパズルっぽく感じるもうひとつの理由を挙げてみます。
それは「システム自体が一定のルールを規定していない」ことにあると考えます。
最初に定義したとおり、ゲームとは一定のルールのもとで運用されるものと考えます。
つまり、文字が読める或いは言語を理解できるならば
・誰がいつどのようなメンバーと
遊んだとしても「同じ運用」になるものが「一定のルール」と呼ぶものなのではないでしょうか。
将棋の香車を斜めに動かして良い、オセロの駒は挟めるものがなくても置いて良い。そんな運用は聞いたことがないように、ゲームのルールとは常に一様の運用をされてしかるべきと考えます。
(だからこそ、システムが自分の希望と合致しないならば別のシステムを探せ、と言います。枝葉末節ならばともかくシステムの根幹に手を入れるのは私にとって言語道断の行為です)
故に、恣意と舌先で運用が変わるシステムであるAの魔法陣は、ゲームっぽくないのです。
PR
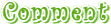
No title
○僕の雪さんの記事の理解
1)前半では、ゲームにもパズルにも属しているものがあってAマホにしろTRPGにしろそうですよって話。
2)後半はルールのあるなしによってゲームか否か決める話ですね。
1)に関しては確かにその通りだと思います。
コスティキャンの定義を使わないなら”パズルなのかゲームなのか”という問いがそもそも成立しないんですね。ゲームでありパズルであるということがありえるわけです。
ただ用語しては”群”じゃなくて”集合”にして欲しかったです。
群っいうのは、要素同士演算ができるときに使われる概念ですよ。1+2=3で1も自然数2も自然数なら3も自然数みたいな。今回は神経衰弱+ブラックジャックが意味が分からず、遊戯の間になにか演算ができるわけではありませんw。まぁ細かいところですが。
2)に関しては僕は別の意見を持っています。
ルールのあるものがゲームであるという立場も歴史的にはあり、それはそれで正等なものなのです、
しかし、個人的には、この立場はほんとはルールがあるのに、それに気づかない可能性を助長するからです。僕はなりちゃだろうが、ままごとだろうが、暗黙のルールはあると思っています。
Aマホでいうなら、例えば”PLが順番に行動宣言をする”など普通のTRPGより厳しいルールが守られている部分もありますよね。Aマホにだってルールは厳密にあるかと。行動の難易度がGMによって違うのはSWなんかでもありえることです。
まぁ”どんな遊戯にも明示的にしろ暗黙にしろルールはある”というのは事実というより僕の考えなので、異見はあると思いますけど。
1)前半では、ゲームにもパズルにも属しているものがあってAマホにしろTRPGにしろそうですよって話。
2)後半はルールのあるなしによってゲームか否か決める話ですね。
1)に関しては確かにその通りだと思います。
コスティキャンの定義を使わないなら”パズルなのかゲームなのか”という問いがそもそも成立しないんですね。ゲームでありパズルであるということがありえるわけです。
ただ用語しては”群”じゃなくて”集合”にして欲しかったです。
群っいうのは、要素同士演算ができるときに使われる概念ですよ。1+2=3で1も自然数2も自然数なら3も自然数みたいな。今回は神経衰弱+ブラックジャックが意味が分からず、遊戯の間になにか演算ができるわけではありませんw。まぁ細かいところですが。
2)に関しては僕は別の意見を持っています。
ルールのあるものがゲームであるという立場も歴史的にはあり、それはそれで正等なものなのです、
しかし、個人的には、この立場はほんとはルールがあるのに、それに気づかない可能性を助長するからです。僕はなりちゃだろうが、ままごとだろうが、暗黙のルールはあると思っています。
Aマホでいうなら、例えば”PLが順番に行動宣言をする”など普通のTRPGより厳しいルールが守られている部分もありますよね。Aマホにだってルールは厳密にあるかと。行動の難易度がGMによって違うのはSWなんかでもありえることです。
まぁ”どんな遊戯にも明示的にしろ暗黙にしろルールはある”というのは事実というより僕の考えなので、異見はあると思いますけど。
No title
書き方が悪かったか。若干齟齬が生じているようです。
前半についてはそのとおりです。
ただ、「群」は”ぐん”じゃなくて”むれ”と読んで欲しかった(笑)
一般的な言葉として(羊の群れ、人の群れ)の延長線上で使った単語なのでそこに突っ込まれると。
後半部分についてですが、これは書き方が悪かったのでこういった誤解が生じても仕方なかったと反省しています。
「一定のルールがない」というのは成功要素の抽出とその成功要素が「その場面において本当に成功することに寄与する事柄なのか」の裁定に関する明確な規定がされていない、ということを言いたかったのです。
つまるところ、システムの一番の目玉(と私は感じています)にかかわるルールがあやふやだ、と言いたいのです。
> 僕はなりちゃだろうが、ままごとだろうが、
> 暗黙のルールはあると思っています。
これについて少しばかり。
ままごとは相当の度合で完成した「RP」の一形態だと私は考えています。
不文律を暗黙のルールと呼ぶならば、まさしくそれが存在していると考えています。
なりちゃについては内容を知りませんし調べるほどに興味もないのでコメントは割愛します。
> ほんとはルールがあるのに、それに気づかない
> 可能性を助長するからです。
これは微妙なところですが、場面によって運用・適用が変わるようなルールならば「それがゲームであると規定するルールではない」という程度にお応えします。
ゲームではないものにもルールがあるのは当たり前で、行動の自由を許されている行為には必ずルール(規則・規定)が伴うはずです。
ところで座布団さんの指摘を受けて、私が長年感じていた「なぜTRPG者はTRPGを特別なものとして扱いたがるのか」という疑問と「なぜTRPGはゲームらしくないのか」という疑問に一定の答えが出た気がします。
前半についてはそのとおりです。
ただ、「群」は”ぐん”じゃなくて”むれ”と読んで欲しかった(笑)
一般的な言葉として(羊の群れ、人の群れ)の延長線上で使った単語なのでそこに突っ込まれると。
後半部分についてですが、これは書き方が悪かったのでこういった誤解が生じても仕方なかったと反省しています。
「一定のルールがない」というのは成功要素の抽出とその成功要素が「その場面において本当に成功することに寄与する事柄なのか」の裁定に関する明確な規定がされていない、ということを言いたかったのです。
つまるところ、システムの一番の目玉(と私は感じています)にかかわるルールがあやふやだ、と言いたいのです。
> 僕はなりちゃだろうが、ままごとだろうが、
> 暗黙のルールはあると思っています。
これについて少しばかり。
ままごとは相当の度合で完成した「RP」の一形態だと私は考えています。
不文律を暗黙のルールと呼ぶならば、まさしくそれが存在していると考えています。
なりちゃについては内容を知りませんし調べるほどに興味もないのでコメントは割愛します。
> ほんとはルールがあるのに、それに気づかない
> 可能性を助長するからです。
これは微妙なところですが、場面によって運用・適用が変わるようなルールならば「それがゲームであると規定するルールではない」という程度にお応えします。
ゲームではないものにもルールがあるのは当たり前で、行動の自由を許されている行為には必ずルール(規則・規定)が伴うはずです。
ところで座布団さんの指摘を受けて、私が長年感じていた「なぜTRPG者はTRPGを特別なものとして扱いたがるのか」という疑問と「なぜTRPGはゲームらしくないのか」という疑問に一定の答えが出た気がします。
No title
なんでルールについて端折った書き方になったのか弁解を。
私にとってはどんなささいな物事にもルールが存在しているというのは自明のことなので、わざわざ断るまでもない。
…という意識がはたらいたようです。
私にとってはどんなささいな物事にもルールが存在しているというのは自明のことなので、わざわざ断るまでもない。
…という意識がはたらいたようです。
最新記事
ぶくろぐ
カテゴリー
カレンダー
アーカイブ




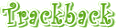



 管理画面
管理画面
