管理人がつれづれに書き散らかしたあれこれ
2025.11.16
[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
2008.03.09
また宿題を持ち帰ってしまった。
しかも2個目の宿題から手をつけるという。
1個目は忘れたわけじゃあ、ありません。ただ。
時間をおいたら頭の中でまとめた文がどこかすっとんだだけで…。
さてはて、今回のお題は「なぜ”Aの魔法陣”はパズル的であると感じられるのか?」
まずは今回使う用語と、比較する対象を明示するところから始めましょうか。
1個目は忘れたわけじゃあ、ありません。ただ。
時間をおいたら頭の中でまとめた文がどこかすっとんだだけで…。
さてはて、今回のお題は「なぜ”Aの魔法陣”はパズル的であると感じられるのか?」
まずは今回使う用語と、比較する対象を明示するところから始めましょうか。
比較する対象
・Aの魔法陣
・水平思考推理ゲーム
使う用語
・ゲーム
これだけだと何の事だかさっぱりですね。
もう少し内容をかみ砕いていきましょう。今回はTRPGとパズルの関係に言及したいので2)の遊戯について更に引用します。
・遊戯
…また”勝負ごと”が出てきました。
となれば、どうしても避けて通れない道のようです。
・勝負事
これでだいぶ意味が通じるようになってきましたね。
ここで私は以下の文において使用するゲームという語について、次の意味で使うことを宣言します。
・パズル
はて、”判じもの”などという耳慣れない単語が出てきました。今回ももう少し噛み砕いていきましょう。
・考え物
・判じもの
意味が通じましたね。
では改めて私は以下の文において使用するパズルという語について、次の意味で使うことを宣言します。
ところで、ゲームに関しては『クロフォードのゲーム論』という一部TRPG者には有名な文献があるのですが、知らない人は知らないでしょうし、読んだところでそうそう理解がしやすい文でもありません。
そもそも、論文に書かれていることが一般的な感覚からずれていては意味がないので(TRPG者はいつだって自分が逸般人であることを忘れてはいけません!)、ここからの引用ならば納得もいくだろう、という『広辞苑』にご登場願いました。
なんだか前置きが長くなりました。そろそろ本題に行きましょう。
そもそも水平思考推理ゲームって何さ?
という声が聞こえてきそうな気がします。
この水平思考推理ゲーム、私が出会ったきっかけというのはこの記事を通してなのですが、簡単にいうならばなぞなぞの一種です。
これは英語で「Lateral Thinking Puzzles」という名前であり、日本語ではゲームと翻訳されていますが、パズルの一種(なぞなぞはパズル)です。
しかし、この水平思考推理ゲームには明確なルールがあります。
これだけでは何の事だかさっぱりですね。
では、水平思考推理ゲームで最も有名な命題であると思われる『ウミガメのスープ』を以下に掲示しましょう。
当然ですが、出題者は最初に正解を決めておかなければいけませんし(そうじゃなければ質問に答えられません!)、その正解は理論的につじつまがあっていなければいけません。
この命題に対して、回答者と出題者が質疑応答を行い、謎を解く、というのがゲームの趣旨です。
何かに似ていると思いませんか?
そうです。TRPGのミステリ・シナリオです。
TRPGのミステリ・シナリオからRPの部分を取り払うと水平思考推理ゲームになる、と私は考えています。
ゆえに、私は、水平思考推理ゲームは限りなくゲームに近いパズルであると考えます。
さて、お次はTRPGのタイトルが一である、”Aの魔法陣”です。
これは第四世代を標榜するタイトルで、一般的にイメージするTRPGとはちょっと?かなり?違ったシステムになっています。
どのくらい違うのかというと、きれいにまとめてくださったテキストがあるので引用させていただきましょう。
引用元はこちら
とはいえ、私自身ルールブックを読んだだけではイメージが掴めなかったシステムですので例を提示しつつ進めていきましょう。
Aの魔法陣はまず、SD(一般的なシステムのGM。Aの魔法陣においては”セッションデザイナー”と呼ばれ、命題の作成とルール裁定は行うがそれ以外のことは一切行わない)が命題を提示することからセッションは開始されます。
これは実際のプレイから引用させていただきましょう。といっても私が参加したことがあるのは某布と綿の合成物の方がSDされたものだけなのですが…。
抽出条件とかいきなり出てきても困りますね。
Aの魔法陣では各キャラクターは”成功要素”と呼ばれるものを持っています。
他のシステムでは技能や特徴などに相当するものでしょうか。(とはいえ汎用性はありませんが…)
この要素を提示して難易度を”削って”いく、というのがセッション進行になります。(実際の進行が見たいかたはこちらをどうぞ)
…Aの魔法陣がなぜパズル的であるのか、というのはこの構造そのものが原因であると思っています。
最初に定義したとおり、思考するだけではゲームと呼ばないわけですが、Aの魔法陣には明確なルールがあります。
ただし、キャラクター作成と各行動の難易度決定にだけ。
進行中の会話をかみ砕くとだいたい以下のような感じになります。
と。
…SDと会話しているのはPLですね。
興味深いことに、Aの魔法陣ではPCは文字通りデータだけの存在です。
PCの持つ”成功要素”を用いて命題に対する”最適解”を考える。
そういった側面が強いシステムです。
もっと突き詰めるならば、先に命題が提示されている場合には、その命題に対し最も有効な作戦をとれるPLを1名、行動が取れるPC(PL)を難易度/2+1以上揃えれば自動的に成功することになります。
(この例は実際にルールブックのコラムにあります。)
ここまで来ると、もはやTRPGの”P”がどこかに行ってしまっていますね。
さて、このAの魔法陣を”まじめ”に遊ぶとこうなるのではないか?と考えると、何かに似てきます。
そうです、先にあげた水平思考推理ゲームの出題者と回答者の問答です。
水平思考推理ゲームも一応ルールらしきルールはありましたが、やはりパズルでした。
Aの魔法陣はどうでしょう?
規定されているルール部分が水平思考推理ゲームに限りなく近い範囲ではないでしょうか?
進行自体は最適解の探り合い、ルール規定部はごく最低限。
ゆえに、私は、Aの魔法陣は限りなくパズルに近いゲームであると考えるのです。
ゲームに限りなく近いパズルとパズルに限りなく近いゲームの違いとは何でしょうか?
思うに本質的な差というものはないのでしょう。
ただ、取り組む側の気持ちが違ってきます。
ゲームに限りなく近いパズルに取り組む側、というのは”これはパズルだ”と思いとりかかるでしょう。
だが、始めてみるとそのパズルはあまりパズルっぽくない?ゲーム的側面が強い?ことに気がつきます。
ゆえに、「これ、パズルじゃなくてゲームなんじゃないかなぁ?」と感じるのでしょう。
逆に、パズルに限りなく近いゲームに取り組む側、というのはやはり”これはゲームだ”と思いとりかかるでしょう。
やはりこちらも、始めてみるとそのゲームはあまりゲームっぽくない?パズル的側面が強い?ことに気がつきます。
ゆえに、「これは、ゲームじゃなくてパズルなんじゃないかなぁ?」と感じるのでしょう。
TRPGを標榜するゆえに、Aの魔法陣はパズル的であると感じられるのだと考えます。
おまけ:
TRPGの勝敗って何?
簡単に言うならば『場にいる全員が愉しめれば勝ち』、の一言に尽きると私は考えています。
GM vs PLという構図もそれはそれで楽しみがあるのですが、もはやそういったヘビーな遊び方は時代に合わなくなっているのでしょう。
上の文で勝ち負けを伴うことについて全くと言っていいほど触れていないのは、この辺りの事情になります。
・Aの魔法陣
・水平思考推理ゲーム
使う用語
・ゲーム
1)競技。試合。勝負。
2)遊戯。勝負事。
(3以降省略)
引用:広辞苑 第四版
これだけだと何の事だかさっぱりですね。
もう少し内容をかみ砕いていきましょう。今回はTRPGとパズルの関係に言及したいので2)の遊戯について更に引用します。
・遊戯
1)あそびたらむれること。あそび。ゆげ。ゆうげ。
2)幼稚園・小学校などで、運動や娯楽、または社会性を身につけることなどを目的として一定の方法で行う遊び。
3)勝負ごと。
引用:広辞苑 第四版
…また”勝負ごと”が出てきました。
となれば、どうしても避けて通れない道のようです。
・勝負事
1)かちまけを争うわざ。
2)ばくち。とばく。
引用:広辞苑 第四版
これでだいぶ意味が通じるようになってきましたね。
ここで私は以下の文において使用するゲームという語について、次の意味で使うことを宣言します。
ゲームとは、勝ち負けを伴う娯楽であり、一定の方法(=明確なルール)で行う遊びである。
・パズル
1)考え物。判じもの。
引用:広辞苑 第四版
はて、”判じもの”などという耳慣れない単語が出てきました。今回ももう少し噛み砕いていきましょう。
・考え物
1)よく考えてから決すべき事柄。また、疑念の余地のあるものごと。
2)考えてあてるもの。判じもの。
引用:広辞苑 第四版
・判じもの
謎の一種。文字・絵などに或る意義を寓して、それを判じさせるもの。
引用:広辞苑 第四版
意味が通じましたね。
では改めて私は以下の文において使用するパズルという語について、次の意味で使うことを宣言します。
パズルとは、文字・絵・言葉等を用い謎(=命題)を提示し、それに対し思考を以て判断を行うものである。
ところで、ゲームに関しては『クロフォードのゲーム論』という一部TRPG者には有名な文献があるのですが、知らない人は知らないでしょうし、読んだところでそうそう理解がしやすい文でもありません。
そもそも、論文に書かれていることが一般的な感覚からずれていては意味がないので(TRPG者はいつだって自分が逸般人であることを忘れてはいけません!)、ここからの引用ならば納得もいくだろう、という『広辞苑』にご登場願いました。
なんだか前置きが長くなりました。そろそろ本題に行きましょう。
そもそも水平思考推理ゲームって何さ?
という声が聞こえてきそうな気がします。
この水平思考推理ゲーム、私が出会ったきっかけというのはこの記事を通してなのですが、簡単にいうならばなぞなぞの一種です。
これは英語で「Lateral Thinking Puzzles」という名前であり、日本語ではゲームと翻訳されていますが、パズルの一種(なぞなぞはパズル)です。
しかし、この水平思考推理ゲームには明確なルールがあります。
- 出題者は一人もしくは数人の回答者に対し問題を提示する
- 回答者は出題者に対し質問を投げかけることができる
- 出題者は回答者からの質問に対し「はい」「いいえ」「関係ない」の三通りのうちどれかを答えなくてはいけない
- 出題者は回答者からの質問に対し嘘をついてはいけない
これだけでは何の事だかさっぱりですね。
では、水平思考推理ゲームで最も有名な命題であると思われる『ウミガメのスープ』を以下に掲示しましょう。
レストランで”ウミガメのスープ”を食べた男が自殺した。
なぜ?
当然ですが、出題者は最初に正解を決めておかなければいけませんし(そうじゃなければ質問に答えられません!)、その正解は理論的につじつまがあっていなければいけません。
この命題に対して、回答者と出題者が質疑応答を行い、謎を解く、というのがゲームの趣旨です。
何かに似ていると思いませんか?
そうです。TRPGのミステリ・シナリオです。
TRPGのミステリ・シナリオからRPの部分を取り払うと水平思考推理ゲームになる、と私は考えています。
ゆえに、私は、水平思考推理ゲームは限りなくゲームに近いパズルであると考えます。
さて、お次はTRPGのタイトルが一である、”Aの魔法陣”です。
これは第四世代を標榜するタイトルで、一般的にイメージするTRPGとはちょっと?かなり?違ったシステムになっています。
どのくらい違うのかというと、きれいにまとめてくださったテキストがあるので引用させていただきましょう。
第1世代…D&D(物理法則に関する共通認識をシステムで提供)
第2世代…Rune Quest(物理法則と背景設定に関する共通認識をシステムで提供)
第3世代…FEAR系(物理法則と背景設定と物語に関する共通認識をシステムで提供)
第4世代(?)…Aの魔法陣(システムでは共通認識を提供しない)
引用:氷川TRPG研究室
引用元はこちら
とはいえ、私自身ルールブックを読んだだけではイメージが掴めなかったシステムですので例を提示しつつ進めていきましょう。
Aの魔法陣はまず、SD(一般的なシステムのGM。Aの魔法陣においては”セッションデザイナー”と呼ばれ、命題の作成とルール裁定は行うがそれ以外のことは一切行わない)が命題を提示することからセッションは開始されます。
これは実際のプレイから引用させていただきましょう。といっても私が参加したことがあるのは某布と綿の合成物の方がSDされたものだけなのですが…。
M*無事に生き残る:
難易度26:判定単位100:制限時間30分(電車が爆発する?)
1ターン30分:難易度決定の前提 30分(つまり1ターン)、日本人の場合:抽出条件は地下鉄から脱出するのにあいそうなもの。
抽出条件とかいきなり出てきても困りますね。
Aの魔法陣では各キャラクターは”成功要素”と呼ばれるものを持っています。
他のシステムでは技能や特徴などに相当するものでしょうか。(とはいえ汎用性はありませんが…)
この要素を提示して難易度を”削って”いく、というのがセッション進行になります。(実際の進行が見たいかたはこちらをどうぞ)
…Aの魔法陣がなぜパズル的であるのか、というのはこの構造そのものが原因であると思っています。
最初に定義したとおり、思考するだけではゲームと呼ばないわけですが、Aの魔法陣には明確なルールがあります。
ただし、キャラクター作成と各行動の難易度決定にだけ。
進行中の会話をかみ砕くとだいたい以下のような感じになります。
PL:αという行動の難易度はいくつですか?
SD:Xです。
PL:βという行動をしつつαを行うならば難易度はいくつですか?
SD:前提置換されてXからYに下がります。
と。
…SDと会話しているのはPLですね。
興味深いことに、Aの魔法陣ではPCは文字通りデータだけの存在です。
PCの持つ”成功要素”を用いて命題に対する”最適解”を考える。
そういった側面が強いシステムです。
もっと突き詰めるならば、先に命題が提示されている場合には、その命題に対し最も有効な作戦をとれるPLを1名、行動が取れるPC(PL)を難易度/2+1以上揃えれば自動的に成功することになります。
(この例は実際にルールブックのコラムにあります。)
ここまで来ると、もはやTRPGの”P”がどこかに行ってしまっていますね。
さて、このAの魔法陣を”まじめ”に遊ぶとこうなるのではないか?と考えると、何かに似てきます。
そうです、先にあげた水平思考推理ゲームの出題者と回答者の問答です。
水平思考推理ゲームも一応ルールらしきルールはありましたが、やはりパズルでした。
Aの魔法陣はどうでしょう?
規定されているルール部分が水平思考推理ゲームに限りなく近い範囲ではないでしょうか?
進行自体は最適解の探り合い、ルール規定部はごく最低限。
ゆえに、私は、Aの魔法陣は限りなくパズルに近いゲームであると考えるのです。
ゲームに限りなく近いパズルとパズルに限りなく近いゲームの違いとは何でしょうか?
思うに本質的な差というものはないのでしょう。
ただ、取り組む側の気持ちが違ってきます。
ゲームに限りなく近いパズルに取り組む側、というのは”これはパズルだ”と思いとりかかるでしょう。
だが、始めてみるとそのパズルはあまりパズルっぽくない?ゲーム的側面が強い?ことに気がつきます。
ゆえに、「これ、パズルじゃなくてゲームなんじゃないかなぁ?」と感じるのでしょう。
逆に、パズルに限りなく近いゲームに取り組む側、というのはやはり”これはゲームだ”と思いとりかかるでしょう。
やはりこちらも、始めてみるとそのゲームはあまりゲームっぽくない?パズル的側面が強い?ことに気がつきます。
ゆえに、「これは、ゲームじゃなくてパズルなんじゃないかなぁ?」と感じるのでしょう。
TRPGを標榜するゆえに、Aの魔法陣はパズル的であると感じられるのだと考えます。
おまけ:
TRPGの勝敗って何?
簡単に言うならば『場にいる全員が愉しめれば勝ち』、の一言に尽きると私は考えています。
GM vs PLという構図もそれはそれで楽しみがあるのですが、もはやそういったヘビーな遊び方は時代に合わなくなっているのでしょう。
上の文で勝ち負けを伴うことについて全くと言っていいほど触れていないのは、この辺りの事情になります。
PR
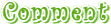
No title
要するに
0 なぞなぞ⊂パズルを前提とする
1 ”水平思考ゲーム⊂なぞなぞ”である。
?を”だいたい同じ”ことを表す記号だとして
2 水平思考ゲーム?RPぬきのミステリシナリオ
?Aの魔法陣である
よってAの魔法陣はだいたいなぞなぞであり、パズルに属す。このような論理展開でしょうか。
この意見には納得できます。僕もそのように思います。
==================
大まかに納得した上で細かい違いを述べますと
水平思考ゲームのやミステリシナリオの場合は”真相”があるのに対しAマホでは真相がありません。
たぶんAマホを真相ありのゲームにするとつまらないんですよね。SDは漠然とした考えしか用意しないほうがPLの発想が生かされて良いと思います。
ちょっと話がそれますが
3+4=?で7を答えさせるのはパズル的だと思うのですが、?+?=7で?をうめるのも雪さんの感覚ではやはりパズルでしょうかね。後者は答えに自分の独創性をだせるという点が少々特徴的ですが。
==================
また水平思考ゲームとRPG(Aマホ含む)の違いは自分でPCを用意するところにもあるかもしれません。そうするとどうしても、”自らの持っている資源をいかに生かすか”という問題が生じ、これはRPG的なように思えます。
0 なぞなぞ⊂パズルを前提とする
1 ”水平思考ゲーム⊂なぞなぞ”である。
?を”だいたい同じ”ことを表す記号だとして
2 水平思考ゲーム?RPぬきのミステリシナリオ
?Aの魔法陣である
よってAの魔法陣はだいたいなぞなぞであり、パズルに属す。このような論理展開でしょうか。
この意見には納得できます。僕もそのように思います。
==================
大まかに納得した上で細かい違いを述べますと
水平思考ゲームのやミステリシナリオの場合は”真相”があるのに対しAマホでは真相がありません。
たぶんAマホを真相ありのゲームにするとつまらないんですよね。SDは漠然とした考えしか用意しないほうがPLの発想が生かされて良いと思います。
ちょっと話がそれますが
3+4=?で7を答えさせるのはパズル的だと思うのですが、?+?=7で?をうめるのも雪さんの感覚ではやはりパズルでしょうかね。後者は答えに自分の独創性をだせるという点が少々特徴的ですが。
==================
また水平思考ゲームとRPG(Aマホ含む)の違いは自分でPCを用意するところにもあるかもしれません。そうするとどうしても、”自らの持っている資源をいかに生かすか”という問題が生じ、これはRPG的なように思えます。
No title
> 水平思考ゲームのやミステリシナリオの場合は”真相”があるのに対しAマホでは真相がありません。
水平思考推理ゲームは明らかに「出題者からの命題を解く」ことが目的ですね。
ミステリシナリオはどうでしょう?確かに「事件の真相を暴く」ことは目的のひとつなのでしょうけれども、この真相に関しては必ずしも解明される必要はありません。
しかし、事件を扱う以上は真相がなければグダグダになりますね。
では、Aの魔法陣はどうでしょうか?
事件を扱うわけではないですから(扱うものも中にはあるでしょうけれども)真相はほぼ存在しないでしょうけれども、『使命(やらなければいけないこと)』があるので、結局似たようなものだと考えています。
> 3+4=?で7を答えさせるのはパズル的だと思うのですが、
> ?+?=7で?をうめるのも雪さんの感覚ではやはりパズルでしょうかね。
面白いたとえが出てきました。
3+4=7というのは間違いなくパズルの一種ですね。正解がひとつであるパズルです。
そして?+?=7もまた、私にとってはパズルです。
これは正解が7個ある(並び順も含めるならば14)パズルでしょう。なにも、パズルの正解は1つでなければいけない、というルールはないでしょう。
本文でも述べていますが、「思考を伴う」だけではゲームとは呼ばないと考えています。
本文ではあえてはしょっていますが、ゲームの場合には『実際に遊ぶ過程を通して一定の社交性が身につく』というのも重要な要素だと実は考えています。
が、今回の話に関しては関係がないことと判断して割愛しました。
> ”自らの持っている資源をいかに生かすか”という問題が生じ、これはRPG的なように思えます。
これに関してはコメント欄に記載するにはあまりにもボリュームが大きすぎますね。
この件に関しては『RPGって何なの?』というあたりから一本の記事にしようかと思います。
水平思考推理ゲームは明らかに「出題者からの命題を解く」ことが目的ですね。
ミステリシナリオはどうでしょう?確かに「事件の真相を暴く」ことは目的のひとつなのでしょうけれども、この真相に関しては必ずしも解明される必要はありません。
しかし、事件を扱う以上は真相がなければグダグダになりますね。
では、Aの魔法陣はどうでしょうか?
事件を扱うわけではないですから(扱うものも中にはあるでしょうけれども)真相はほぼ存在しないでしょうけれども、『使命(やらなければいけないこと)』があるので、結局似たようなものだと考えています。
> 3+4=?で7を答えさせるのはパズル的だと思うのですが、
> ?+?=7で?をうめるのも雪さんの感覚ではやはりパズルでしょうかね。
面白いたとえが出てきました。
3+4=7というのは間違いなくパズルの一種ですね。正解がひとつであるパズルです。
そして?+?=7もまた、私にとってはパズルです。
これは正解が7個ある(並び順も含めるならば14)パズルでしょう。なにも、パズルの正解は1つでなければいけない、というルールはないでしょう。
本文でも述べていますが、「思考を伴う」だけではゲームとは呼ばないと考えています。
本文ではあえてはしょっていますが、ゲームの場合には『実際に遊ぶ過程を通して一定の社交性が身につく』というのも重要な要素だと実は考えています。
が、今回の話に関しては関係がないことと判断して割愛しました。
> ”自らの持っている資源をいかに生かすか”という問題が生じ、これはRPG的なように思えます。
これに関してはコメント欄に記載するにはあまりにもボリュームが大きすぎますね。
この件に関しては『RPGって何なの?』というあたりから一本の記事にしようかと思います。
最新記事
ぶくろぐ
カテゴリー
カレンダー
アーカイブ




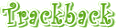



 管理画面
管理画面
